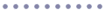在学生VOICE
本学に進学してよかったことは
-
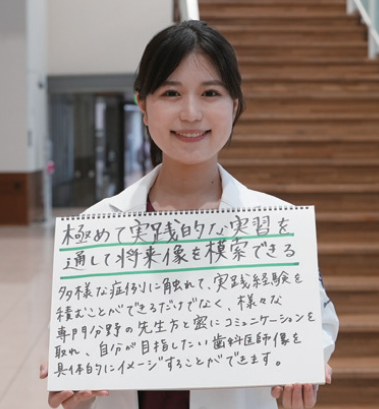
歯学科
M. N.さん -
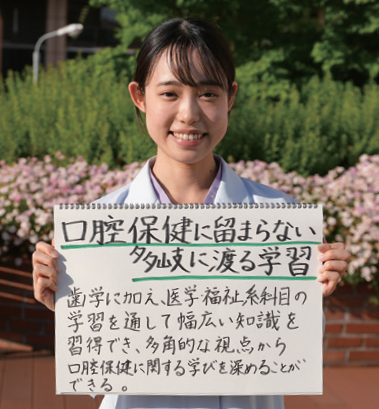
口腔保健学科
口腔保健衛生学専攻
T. K.さん -
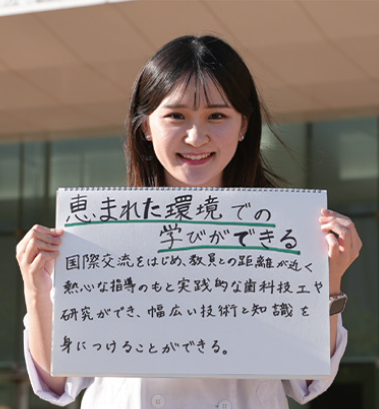
口腔保健学科
口腔保健工学専攻
N. H.さん
その他の声
- 卒業後も縦横の関係が良好で医学部との交流も他大学にはない綿密さがある
- 最高学年時に多くの臨床ケースの実習が課され、卒業後直ちに一般臨床に役立つよう教育された
- 高度な研究生活、豊富で多様な臨床経験を積むことができたと思う
参考:2019年度実施分【歯学科】卒業生進路アンケート集計結果(統合教育機構 教学IRチーム)
回答者496名(1952年~2019年東京医科歯科大学卒業生)
出典:2022年 歯学部概要
歯学科

基礎から応用、全身から頭頸部への探求
歯学科6年
原田 健太郎
本学では、2年生から専門教育が始まります。私たちの専門教育は、講義・実習を通して解剖学、組織学、生理学など全身の基礎医学から始まります。全身の解剖学実習や歯の解剖学をはじめとする幅広くかつ専門性の高い実習では将来の歯科医師としての基礎をつくります。
基礎医学を一通り学ぶと臨床歯学の講義・実習が始まり、顔面・口の中の病気・治療に関して学びます。模型、人工や実際の歯を用いた実習では担当の先生から丁寧な指導が受けられます。コロナ禍であっても、感染対策に配慮した上で学びを止めることなく、以前と変わらない充実した実習を行っています。
5年生の後半からは、今までの学習の集大成である本学の病院D棟にある学生クリニックで、指導医の監督のもと来院される実際の患者さんに虫歯、歯周病、かぶせ物、抜歯、入れ歯といった治療を学生が主体となって行っています。事前学習とより一層の責任が求められる実習ですが、他にはない本学ならではの取り組みだと思います。
出典:2023年 大学案内
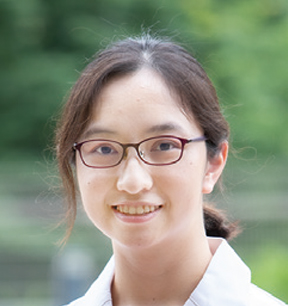
実臨床に近い環境、
一筋縄ではない診療、筆舌しがたい感動
歯学科6年
張 美旭
包括臨床実習では、学生一人につき10~20名の患者さんを担当し、各分野の指導医の下で患者さんとの関係構築、診断、治療、経過の観察など診療の全ステップを行い、実際の臨床現場とほぼ同じ環境を体験します。
診療を恙無く進めるための予習、予約間隔の設定、患者さんの全身疾患が多く対応が必要な場合や治療する歯が著しく傾斜している場合、患者さんに治療方針に納得して頂けない場合などに多分野の知識を総合して考えることなど大変なことも多々ありますが、知識が経験としてしっかり身につくようになります。難題があった際には同期と助け合い、先生と話し合い、人間的にも成長します。そして問題を解決して患者さんの笑顔を見ることができた時には、座学やマネキンを用いた模型実習にはない達成感が得られます。
私は上顎の全部床義歯を完成させた時、患者さんに「これほど吸い付く入れ歯は人生で初めてだ」と喜んで頂け、感無量でした。
出典:2023年 大学案内

毎日新しく
学ぶことが尽きない包括臨床実習
歯学科6年
秦 健太
包括臨床実習では、学生一人につきおよそ20名の患者さんを担当します。各分野の先生方のご指導の下、学部生の段階から治療そのものを行うことができる環境は本当に恵まれているものだと思います。毎回の診療は、事前に治療の流れを指導医の先生と打ち合わせをして十分な準備を行った上で臨みます。その分準備は大変ですが、患者さんの痛みや不安に寄り添って信頼関係を構築していくという歯科医師としての基本姿勢を学ぶことができます。教科書での勉強やマネキンを使っての実習だけでは分からなかった治療の難しさがあり、この実習を通して自分の未熟さを毎回痛感させられますが、できることが少しずつ増えたり、治療後に患者さんが笑顔を見せてくれたりする時にはとてもやりがいを感じます。
6年間を共にする同期とは互いに切磋琢磨しながら充実した学生生活を送っています。
出典:2022年 大学案内

King’s College Londonでの
研究実習を終えて
歯学科6年
松村 俊佑
私は Centre for Craniofacial & Regenerative Biology, Dental Faculty, King's College LondonのDr.Miletich率いるLaboに3ヶ月間派遣していただきました。眼周囲の腺構造の再生におけるWntシグナルの重要性について調べるという内容で、ドライアイの治療に繋がる可能性を秘めた非常に興味深い研究に参加することができました。これまで研究の経験はありませんでしたが、派遣先のDrやPhDの温かい指導のおかげで、順調に研究を進めることができました。海外での長期滞在も初めての経験だったので、研究室内だけでなく、毎日の日常が刺激的で、得るものが沢山ありました。イギリスという異国の地で、多様な考えに日々触れることで、自分自身の視野を広げ、人としても成長できたように感じます。このようなプログラムに参加し、貴重な経験をできたことに心から感謝しています。
本学は海外への窓口が広いことが大きな特徴の一つです。在学中のこのような機会を活かして、将来の選択肢を増やすのもいいのではないでしょうか。
出典:2022年 大学案内
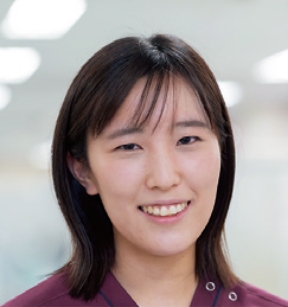
多様性に富んだ
ハーバード大学での貴重な経験
歯学科6年
中山 己緒
私はハーバード大学歯学部のDr.Roland Baronの研究室に3か月間滞在し、骨細胞の骨のリモデリングへの関与といった、骨の分野では世界トップレベルの研究に携わる機会をいただきました。
研究室では研究の手技や学術的な知識だけでなく、世界中から研究者や学生が集まっていたため、様々な国の文化や価値観、医療システムや医療系大学生のカリキュラムなどについて聞き体感することができました。研究経験の浅さや初の海外長期滞在への不安を感じる間もないような、学びの連続で大変充実した日々でした。このようなハイレベルで多様性に富んだ環境で過ごしたことで視野が広がったとともに、モチベーションも向上し研究への興味も更に深まり、自身の将来の進路や勉学の方向性を考えるきっかけになりました。
学部生ながら世界最高峰の環境に身を置けるのは、本学の研究実習の強みです。勉学や研究のみならず、海外での自立した生活も含めて、自身の成長を実感できる貴重な経験になると思います。
出典:2022年 大学案内

世界の歯科医療との関わりへの岐路
タイ王国、Srinakharinwirot University
歯学科5年
原田 健太郎
私が夏の長期休暇でタイのシーナカリンウィロート大学に行ったのは、約3年前2年生の夏のことでした。私にとって外国の歯学部学生との初の交流、また2年生というまた基礎医学を学び始めたころだった私にとって、すべてが新鮮でありました。
10日間の研修は、熱気と活気に満ちた東南アジアの空港から始まり、歯学部の病院見学、実習への参加、さらには現地の歯学部学生とタイ料理を食べたり、週末に観光地を訪れたりと忙しくも、大変密度の濃い経験と世界から見た日本の歯科医療を考えらえる視点を養うことができたと感じています。
帰国後、海外の学生との交流の面白さを感じ、本学を訪れる留学生との交流会等へ参加をし、2020・2021年度では、コロナ禍で直接の留学ができない状況の中でオンラインにてアジア、欧州、米国との交流を継続してきました。
世界各国に多くの協定校を持ち、いかなる状況であっても最善の方法で交流を継続できる力は本学の強みであるかと思います。
出典:2022年 大学案内

協定校との交流について
歯学科5年
浅野 可耀
私は4年生の冬に二つの国際交流を体験しました。
一つ目は、イギリスのキングスカレッジロンドンとのオンライン交流会です。
交流会では、「コロナ禍での歯学教育」「オンライン授業の意義、今後の新しい可能性」など様々なトピックスについて議論をしました。初めてのオンラインでの交流会で緊張しましたが、積極的な意見交換で新しい価値観に触れることができ大変有意義な交流会でした。
二つ目は、アメリカのボストン大学やタイのチュラロンコン大学、イギリスのマンチェスター大学、インドのマニパル大学など世界中の大学が集まるVirtualexchange
programです。このprogramでは世界最高峰の歯学・医学教育を行っている大学の学生と直接交流することで、日頃の授業では得ることができない体験談や国際的な考えを得ることができました。本学の魅力の一つである協定校との交流は、海外学生との絆を深めることや新しい価値観に触れることができる貴重な機会です。
皆さんもぜひ参加してみてください。
出典:2022年 大学案内

日々ステップアップすることが
できる環境
歯学科6年
松本 彩花
歯学科では2年次から口腔内の常態や病態、治療法などはもちろん、人体の解剖学や生理学といった全身についての基礎医学を学びます。
そして5年次の秋から約1年半かけて本学の歯学科で最も特徴的といえる「包括臨床実習」が行われます。この実習では学生専用の診療室で学生の治療に同意していただいた患者さんを担当し、指導医の先生の指導のもとで診療を行います。実際の患者さんと接し診療させていただくことはとても貴重な経験ですので、自然と知識や技術の向上のために励むことができます。また、「包括臨床実習」では指導医の先生方と接する機会が多くありますので、わからないことがあれば指導医の先生に相談しやすく、先生方も親身になって熱心に相談に乗ってくださいます。
加えて本学にはスキルスラボという実習用の歯科ユニットを配置した施設があり、基本的な歯科治療の自己練習を行うことができます。このように知識や技術の向上に励むことのできる環境が整っていることが本学の強みだと感じています。
出典:2022年 大学案内

診療参加型の臨床実習
歯学科6年
紅谷 龍一郎
本学のカリキュラムで一番特徴的であるのは、5年生の秋から6年生にかけて行われる診療参加型の包括臨床実習だと思います。この実習では、歯学部附属病院の学生専用の診療室で、学生の診療に同意していただいた患者さんを学生が担当し、教員の指導の下で治療を行います。他の実習とは異なり、自分自身が患者さんの担当医になるために責任感が生じ、自ずから知識や技術の向上に励むようになります。また、患者さんを治療する際の緊張感や集中力はマネキンを使った実習とは桁外れであり、治療の結果が良好であったときの達成感や、患者さんから感謝の言葉を言われた時の喜びはこの実習でしか味わえません。さらに、先生方や同級生に相談し、協力して問題を乗り越えていく日々は、歯科医師になってからも活きる大切な経験になると思います。この他にも本学では質の高いプログラムが多くあり、恵まれた環境の中で実りのある学生生活を送れることでしょう。
出典:2021年 大学案内

様々な方面からアプローチされた
多様なプログラム
歯学科6年
荒川 玲美
本学には歯学部附属病院があります。約20以上もの診療科が存在し、各学年での病院見学や、5年次後期から実際に患者さんの治療をしていく中で、幅広い選択肢から自分の興味のある分野を見つけることができます。そこで私が興味を持ったのは高齢者歯科学分野です。今や日本は超高齢社会です。ご高齢な方の診療機会が増え、また、病院や診療所へ足を運ぶことが難しい患者さんにも直面します。歯科医師の役割は病院や診療所だけにとどまらず、地域包括ケアシステムの一員としての働きが求められる中、こうした、社会のニーズに合った授業が展開されています。医学部生との合同授業による老年医学や、摂食・嚥下分野による訪問歯科への同行、健康長寿をかかげた授業、多職種連携を掲げた医学部や口腔衛生学科との連携教育などが挙げられます。興味をかきたてられたのも、先生方のきめ細かなご指導、様々な方面からアプローチされた多様なプログラムのためだと思います。
出典:2020年 大学案内
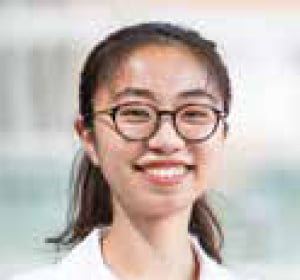
日々成長できる学生生活
歯学科6年
劉 嘉懿
私は大学1年生の時に外国人留学生として入学しました。本学では基礎と臨床の統合型講義・実習がとても充実しています。例えば、2年次以降には、全身の常態と病態を理解できる歯科医師になるために、医学科の学生とともに学習できる医歯学融合教育カリキュラムがあります。そして、各学年に病院の見学実習もあり、臨床現場のイメージを早いうちに掴めることもできます。さらに、5年次の後期から1年間にわたって行われる包括臨床実習があります。学生1人が20人ほどの患者さんを担当し、先生方の指導下で、補綴、保存修復、口腔外科など様々な歯科治療を実際に行うことができます。今まで学んだ知識の応用、さらに新しい知識と技術を身に付け、自分の成長を日々感じる臨床実習です。このように、本学での恵まれた環境の中で、自分が目指す歯科医師に近づけていけると実感できる学生生活がきっと送れると思います。
出典:2018年 大学案内
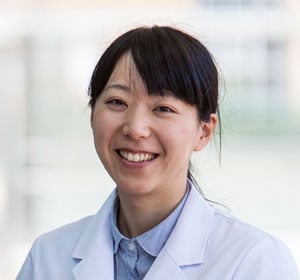
患者さんと向き合い、学べる環境
歯学科6年
武井 潤子
本学では、各学年における病院見学実習、医歯学融合教育、4年次の研究実習などをはじめとするさまざまなプログラムがありますが、最大の特徴は5年次の後期から約1年間にわたって行われる包括臨床実習だと思います。
この実習では、学生1人が20名ほどの患者さんを担当し、先生方の指導の下、医療面接、口腔内診査、治療計画の立案をし、治療を行っていきます。包括臨床実習までに講義や模型を用いた実習を一通り行いますが、実際の患者さんへの治療は緊張感や難易度が格段に上がり、自分の未熟さを痛感する毎日です。しかし、そこで直面した問題について考え、調べ、練習して乗り越えるたびに、新しい知識や技術が増えていき、少しずつ自分の成長を感じることもできます。また、治療が奏功し、感謝の言葉をいただいたときの喜び、達成感は何にも増して大きく、自信にもなります。このように、本学では恵まれた環境の中、実り豊かな学生生活を送れることと思います。
出典:2017年 大学案内
口腔保健衛生学専攻

充実した環境のもと、
口腔保健で社会に貢献する
専門職を目指す
口腔保健学科
口腔保健衛生学専攻4年
寺前 美生
口腔の健康を守ることは、「口から食べる喜び」や「話す楽しみ」を守ることであり、健康寿命の延伸のために重要であると考えられています。口腔の健康を守る専門職として、今後の超高齢社会における歯科衛生士が担う役割は大きくなっています。
口腔保健衛生学専攻では、歯科衛生士や口腔保健衛生学分野の研究者を目指すことができます。1年次には教養科目、2年次には専門科目を学び、3年次にはマネキン実習や学生同士の相互実習で歯科衛生士としての基礎的なスキルを身につけます。3年次後期からは臨床・臨地実習を開始し、これまで身につけてきた知識や技術を応用して実践力を養います。4年次には臨床・臨地実習と平行して卒業研究に取り組み、研究スキルの向上を図ります。
本専攻では、医学科や歯学科をはじめとする他学科との合同演習・合同実習を行うことで、本学ならではの多職種連携を学ぶ機会があることも特徴です。このように、本学では充実した環境のもとで口腔保健を学び、将来社会に貢献できる専門職を目指すことができます。
出典:2022年 大学案内

幅広い視点で口腔保健を学べる、
充実した環境
口腔保健学科
口腔保健衛生学専攻4年
田坂 樹
口腔保健衛生学専攻では、1年次に他学科とともに教養科目を学びます。2年次に専門科目やマネキンを使用した基礎実習、学生同士での相互実習を行い、3年次の後期から本格的に歯学部附属病院での臨床実習が始まります。
臨床実習では、実際に患者さんとの関わりの中でこれまでに学んできた知識や技術を深めることができ、実践力が身につきます。また、他学科との合同実習・演習が盛んに行われており、多職種連携についても学ぶことができます。さらに社会福祉系科目や海外研修制度も充実しており、歯科だけでなく、福祉や医科、グローバルな視点を養うことができます。
本専攻は少人数のため、きめ細かな指導を受けられるとともに、意欲のある仲間と切磋琢磨しながら、楽しく学生生活を送ることができます。このように本学では、充実した環境のもと、口腔保健を通した、医療における実践力・多角的な視点を確実に身につけることができると思います。
出典:2021年 大学案内

レベルの高い知識と技術を学べ、
グローバルな視点で。
口腔保健学科
口腔保健衛生学専攻4年
山中 美優
口腔保健衛生学専攻では、知識と技術を修練するため、1年生から歯科医療機関を見学実習し、2年生からは本格的に基礎実習などを行います。3年生後期からは、臨床・臨地実習として本学附属病院での処置、医学部附属病院さらには外部の様々な医療機関において実習をします。4年生では、臨床・臨地実習と平行して卒業研究を行います。自ら研究のテーマを考え、実験を重ね、考察を繰り返していきます。多職種連携については、医療総合大学の強みを生かし、医学科や歯学科をはじめとする他学科との合同実習・演習があります。
さらに、海外研修奨励制度や短期研修など、海外の大学との交流もあり、積極的にグローバルな視野を備えていくことが出来ます。
本学なら、幅広い知識と正確な技術、多職種連携を担う専門職としての役割、またグローバルな視野を備えた歯科衛生士を目指すことが可能です。
出典:2020年 大学案内

特色ある環境で
トップレベルの口腔保健を学ぶ
口腔保健学科
口腔保健衛生学専攻4年
渡邉 梨奈
「人生100年時代」と言われる昨今、健康寿命の延伸のために、口から食べられることや会話を楽しめることが重要であると考えられており、口腔の健康を守る専門職として歯科衛生士が担う役割が大きくなっています。
口腔保健衛生学専攻では、歯科衛生士や口腔保健衛生分野の研究者、選択科目を履修すれば社会福祉士を目指すことができます。1年次には教養科目、2年次には専門科目を学び、3年次にはマネキン実習や相互実習で基礎的なスキルを身につけます。3年次後期から臨床・臨地実習が開始し、これまでに身につけた知識や技術を応用して実践力を養うことができます。 本専攻では、社会福祉科目も充実していることや、他学科との合同演習・実習が盛んに行われることから、医療と福祉の多角的な視点を実践的に養うことができる環境であることも特徴です。このように、本学では恵まれた環境のもと、トップレベルの専門職を目指すことができることと思います。
出典:2019年 大学案内
口腔保健工学専攻

恵まれた環境で
最先端の技術と幅広い知識を学ぶ
口腔保健学科
口腔保健工学専攻4年
阿部 美香
本専攻は、日本でも数少ない恵まれた環境で幅広く学習できることが魅力だと思います。
実習では従来の方法を中心に補綴装置を製作しますが、3DプリンターやCAD/CAM、スキャナ等の最新の機器を一人一人が扱い、デジタル技術も学ぶことができます。1年次から基礎医学に関する基礎的知識や歯科医療を学習し、4年次には他学科と合同で多職種連携を学ぶ機会もあります。また、国際交流も盛んで、海外渡航が難しい中でもオンラインプログラムが設けられており、海外の学生と交流することができます。
少人数であることから先生方との距離も近く、アットホームで温かい雰囲気があります。授業では、先生方の熱意のこもった手厚いご指導を受けることができ、わからないことがあったときにはすぐに質問できます。定期的に面談もあるため、授業だけではなく学生生活や進路の相談もでき、安心して充実した学生生活を送ることができます。
出典:2023年 大学案内

次世代での活躍を
口腔保健学科
口腔保健工学専攻4年
長谷川 真琴
工学専攻で学べるのは歯科技工学だけではありません。超高齢社会でどのような医療・福祉が必要になるか、CAD/CAM、3Dプリンターなどを中心とするデジタルテクノロジーをどのように利用していくかなど、これからの社会をよりよくするために必要となる知識や技術を得ることができるのです。
また、工学専攻の仲間だけでなく、チーム医療を行うにあたって連携が必要となる他学部などと一緒に学習する場も設けられており、実践的な将来の医療に関わるディスカッションを行えます。PBL形式の授業が多くあるので、学生自ら意欲的に発言する姿勢が身につきます。
また、工学専攻の仲間だけでなく、チーム医療を行うにあたって連携が必要となる他学部などと一緒に学習する場も設けられており、実践的な将来の医療に関わるディスカッションを行えます。PBL形式の授業が多くあるので、学生自ら意欲的に発言する姿勢が身につきます。
本専攻は卒業後の進路に対しても真摯に考えてくださり、就職活動などの際に手厚いサポートを受けることができます。
出典:2021年 大学案内

少人数の良さを生かした
口腔保健学科
口腔保健工学専攻4年
豊田 真奈
工学専攻は基礎医学や歯科医療の概要、先端の材料学などの知識を学べる上に、実習で歯科技工の技術が身につけられる日本で数少ない専攻です。本専攻の魅力は、少人数でアットホームな雰囲気があることです。
先生方との距離が近く、学生一人ひとり丁寧に指導していただけることがとても気に入っています。
また、本専攻では国際交流が盛んです。2年次後期には学生全員に海外研修の機会が与えられ、さらに毎年海外から研修に来た学生を学生自らおもてなしするなど貴重な経験ができます。
1年次の他学科との教養授業、2年次の専門的な基礎実習を終え、3年次ではより専門的な知識、技術を身につけていきます。最新技術のCAD/CAMや3Dプリンターを学ぶ環境も整っており、4年次の臨床実習に向けて学んでいます。レベルの高い実習も多く大変だと感じることもありますが、工学専攻だからこそできるさまざまな経験を得て、充実した学生生活を送っています。
出典:2018年 大学案内

先生との距離の近さが、
技術や知識をさらに深めてくれる
口腔保健学科
口腔保健工学専攻2年
渡辺 舞子
本学は、国内だけでなく国際的にも飛躍できる医療人を育成するためのプログラムが組み込まれていることが大きな特徴です。本専攻では、海外研修として台湾などの大学にいけるのですが、このような機会は他大学ではなかなかできないことだと思います。本専攻は1学年15人程度と少人数なため、先生との距離が近くちょっとした疑問なども尋ねやすい環境にあります。私は他の生徒に比べて不器用で、実習でうまくいかないこともあるのですが、先生が放課後や朝の時間に教えてくださいます。このようなサポートが学生にとって歯科医療技術者として技術や知識をさらに深めてくれるのだと思います。将来は、4年間で学んだ歯科技工の知識を生かし、歯学だけでなく医学の知識もさらに深めて、CAD/CAMの技術向上や歯科医療技術者だからこそできる医療の研究などをしていきたいと思います。
出典:2015年 大学案内

世界で活躍する
歯科医療技術者を目指して
口腔保健学科
口腔保健工学専攻3年
鷹野 夏生
設立から4年目を迎え、新入生を加えて工学専攻にも全学年が揃いました。毎年恒例の新入生歓迎会は今年も盛大に行われ、年々にぎやかになっています。工学専攻が少人数制のため、先生方や先輩とのコミュニケーションがとりやすく、実習や講義での疑問点などを解決しやすい環境にあります。海外研修や英語の授業など、国際的に活躍できる人材の育成に適した環境もこの専攻の魅力の一つです。また、3年生の後期からは、4年生での本格的臨床実習に向けて、過去の臨床例モデルを使用した実践的な実習が始まり、より臨床に即した技術を習得することが出来ます。このような恵まれた環境の中で、私は、しっかりとした歯科技工の知識とそれを使いこなせる技術力を身に着け、世界で活躍できる歯科医療技術者を目指して頑張っていきたいと思います。
出典:2015年 大学案内

活躍する卒業生
歯学科
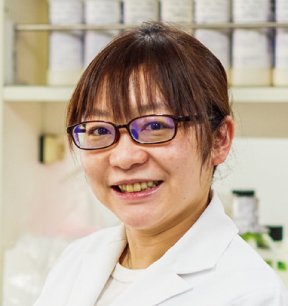
女性上位職登用制度を
活用中です!
大学院医歯学総合研究科 医歯学専攻
口腔機能再構築学講座 口腔生命医科学分野 教授
歯学科 2002年度卒業
片桐 さやか
学生の指導および外来診療に加えチーム一丸となって研究に取り組む
歯周病学分野を目指したきっかけは、学部学生時代の研究体験実習です。臨床講座にいながらも細菌を扱い、分子生物学的なことに触れさせてもらえたことで興味を持つようになりました。
現在、学生の模型実習や患者さんの診療の指導を行い、自身も外来で臨床をしています。歯周病は歯磨きの際の磨き残しが原因なので、患者さん側の協力なしに治すことはできません。歯科医師は歯の汚れが固まってできた歯石を取る治療を行いますが、それでも、その後の患者さんのお手入れが必要です。ですから、私たちの指導やアドバイスを患者さんに守っていただき、歯の状態が良くなられたときには歯科医師としての充実感があります。
また、大学院生やポスドクと8人程度のチームで研究を進めています。歯周病は、口の中の細菌叢のバランスが崩れ、悪い菌が多くなることで腫れて悪化し、最終的には骨が溶けて歯が抜けてしまう病気です。それが糖尿病や早産にも影響すると言われていることから口腔内の細菌叢に注目し、全身の疾患との関わりについて追究しています。新しい発見があったときの喜びはもちろんですが、チームのメンバーは皆外来業務も行っているため、限られた時間の中でお互いにサポートし合っており、チーム一丸となって研究に取り組める今の環境にとても満足しています。
成果や実績が客観的に評価される女性上位職登用制度に申請
女性上位職登用制度に申請したのは、性別や出身といった個人的な枠組みにとらわれず、臨床および研究、教育の成果や実績が客観的に評価されることに魅力を感じたからです。また、私が研鑽期間後の評価で准教授として正式に昇任できれば、分野の教員枠に空きが出ます。それによって別の人がポストに就けるチャンスが生まれ、分野にも貢献できるのではないかと思いました。
キャリアアップ教員に就いたことで、研究費の申請を上位職でできるようになったことが特に良かったと感じています。また、研究支援員配備やオーダーメイド支援などを受ける機会があることも利点として挙げられます。一方、周囲には介護や育児などプライベートな制約によって業務に専念できる時間を十分に確保できない人もいます。その人たちの時間的制約を緩和するシステムがさらに拡充され、より多くの人がキャリアアップを目指せるようになることを期待しています。
今後は、口腔の健康を通して全身の健康に寄与できる研究を行い、臨床にも尽力していきたいと考えています。そして私がこれまで多くの先生方にしていただいたように、研究や臨床の楽しさややりがいを学生たちに伝えていきたいと思います。学生の夢に対するチャレンジを、固定観念にとらわれずにサポートできるリーダーを目指します。

豊富な知識や貴重な経験が
得られる環境で勉強できます!
大学院医歯学総合研究科 医歯学専攻
老化制御学講座 高齢者歯科学分野 准教授
歯学科 2006年度卒業
駒ヶ嶺 友梨子
私は高齢者歯科学分野に所属し、本大学病院歯系診療部門では義歯科という、被せ物や入れ歯を必要とされる患者さんの治療を主に行う外来で診療を行っています。口腔の機能は審美や発音、咀嚼、嚥下などを担い、本大学病院歯系診療部門での歯科治療は、これらの機能を回復し、最終的に、患者さんが健康で質の高い生活を営んでいくことができるように、さまざまな外来の先生方と協力して治療を進めています。
また、近年は高齢者のフレイルが問題となっていますが、そのフレイルも口腔の機能が大いに関連していることが研究で報告されています。フレイル以外にも口腔と全身の関連性は多くの研究で指摘されていて、本学では歯学部内での他分野と連携した研究、さらに医学部とも連携した研究が広く行われています。本学は、口腔から全身の健康を実現するための多くの知識を得ることができ、そして得られた知識を臨床や研究に大いに生かすことができる場であると思います。

「手」と「頭」、
そして「こころ」を学ぶ。
歯学科 2018年度卒業
金 暎勲
多くの患者さんと接しながら、「頭の知識」、「手の技術」、そして何より「こころ」を学べるのは本学ならではのものだと強く思います。
本学のカリキュラムにおける最大のポイントとも言えるこの実習は、学生の勉学のために協力をしてくださる多くの患者さんのお陰でなされています。各専門科の先生方の指導の下、学生自らが治療方針、治療計画、治療そのものまで自主的に行い、1年を経て様々な症例を経験します。先生方の指導を受け、できることが一つ一つ増えていく過程は自分の成長を実感できる良い成長触媒になってくれました。
知識や手技のみならず、学生各自がおよそ20名の患者さんと直接信頼関係を築き、患者さんの痛みや不安を深く理解し、その中で患者さんに対し歯科医師とはどのような存在であるべきかが確立していきます。この「こころ」こそが歯科医師として歩むこれからの人生の中で最も固い基盤になってくれる気がします。
「知」と「癒し」を兼ね備えた歯科医師を目指し精進しましょう。

多くの先生方との出会いが
今のキャリアの礎になった
ミシガン大学歯学部 矯正小児歯科学講座
アシスタントプロフェッサー
歯学科 2003年度卒業
小野 法明
歯科医師の一家に生まれたという小野法明さん。現在は、ミシガン大学歯学部の矯正小児歯科学講座でアシスタントプロフェッサーを務めている。主任研究員として、研究室を主宰しながら、歯学部の学生をはじめ、矯正歯科や小児歯科の研修医の臨床教育に従事しているという。「研究内容は、骨格系幹細胞の役割を生理と病態において解明することを主要なテーマとして掲げ、主にマウスジェネティックスを用いたプロジェクトに取り組んでいます」本学では、学部生時代に基礎分野の教員をはじめとして、様々な価値観を持つ教員と交流する機会を持った。さらに大学院生のときには、臨床では歯科矯正学を専門とする相馬邦道名誉教授研究では難治疾患研究所の野田政樹教授の指導の下で学んだことが、小野さん自身の現在のキャリアの礎になったと語る。
「人生で一番大事な年間を過ごさせていただきました入学したときにはただ漠然と歯科医師になることだけを考えていましたが、多くの先生方との触れ合いを通じて、それは自分としてのキャリアの始まりにすぎないということを確信したのです。本学で学んだことを糧に、今後も教育と研究に勤しんでいきます」
小野さんは、本学にも医師、歯科医師の養成だけでなく、各分野で活躍し得る多様な人材を育ててくれることに期待を寄せている。

世界の歯科医療をリードしよう!
大学院医歯学総合研究科 医歯学専攻
老化制御学講座 高齢者歯科学分野 教授
歯学科 2001年度卒業
金澤 学
私は現在、高齢者歯科学分野に所属し、日本で最多の患者数を誇る歯学部附属病院にて補綴歯科という被せ物や入れ歯を専門とする外来で診療を行いながら、研究と教育に携わっています。超高齢社会を迎えた日本において、口腔から全身の健康を改善するためには何をしたら良いのか、どのような仕組みを考えれば良いのか、そのようなことを考えながら臨床研究を行なっています。
皆さんがご存知の通り、日本は世界で最も高齢化率が高く、それは2060年まで続くと予想されています。超高齢社会における歯科医療サービスに関して、トップランナーとして走り続ける日本を世界中が注目しています。そのような中、本学では欧米やアジアなど様々な国から依頼を受け講演や実習を行ない、また、様々な国の医療関係者が本学の病院や医療システムを学びにきています。超高齢社会に対する優れた医療システム作りに貢献できるのは日本ならでは。そして、世界の歯科医療をリードする優れた臨床研究が行えることは本学ならではの醍醐味です。

世界に誇れる
本学の学部教育プログラム
病院 歯系診療部門 歯科総合診療領域
歯科総合診療科(総合診療歯科学) 准教授
統合教育機構 事業推進部門【兼任】
歯学科 2005年度卒業
則武 加奈子
私は現在、歯科総合診療部の助教として、臨床・研究・教育の業務に携わりながら、厚生労働省医政局歯科保健課に歯科医療技術参与として出向し、歯科医師臨床研修に係る業務などに従事しています。参与という立場を経験し、私自身が担当している診療参加型臨床実習〈包括臨床実習〉、多職種連携教育〈チーム医療入門〉・〈D6-OH4連携実習〉や、その他にも医歯学融合教育、病態科学演習、研究実習や海外研修制度など、本学の多様で特徴ある学部教育プログラムが、国内のみならず世界と比較して誇れるものであることを改めて認識しています。また、これらの職務と3歳になる娘の子育ての両立は、家族や職場の理解とサポートに加え、本学が展開する研究支援員配備事業、学内保育園などの事業にも支えられており、やりがいのある仕事を楽しく続けられています。
今後、歯科医師を目指す皆さんとともに学び、ともに成長できることを願っています。

教育を振興する立場から
大学をみて
歯学科 2001年度卒業
犬飼 周佑
私は本学を卒業後、部分床義歯補綴学分野で大学院生を経たのち、助教として臨床・研究・教育の業務に携わりながら、文部科学省高等教育局医学教育課に技術参与として出向しています。職務としては、主に歯学教育の質向上のための施策に関する業務に就いており、今までの大学での学生教育と歯科医師の養成の経験を生かしながら、社会のために貢献できる高度専門医療人材養成に関する取組にあたっています。
文部科学省での業務を経験し、各大学歯学部の取組状況を知ることで、充実した診療参加型臨床実習をはじめとした本学での学部教育が、日本国内のみならず世界と比較しても高いレベルであり、歯科医学及び歯科医療の発展のために指導的役割を果たすことのできる歯科医師・歯科医療技術者・歯学研究者を養成していることを改めて認識しました。今後も皆さまと共に歯科医学の発展に貢献していけることを願っております。

歯内療法専門医として
抜歯しない治療を広める
歯学科 1988年度卒業
澤田 則宏
在学中に歯内療法の講義を受け、歯を残す治療の大切さに共感しました。その後、米国留学中に歯内療法専門医の存在を知り、その道を志すことに決めたのです。米国では、一般歯科、補綴専門医、口腔病理専門医など様々分野の専門医が連携して治療を進めており、その中の一つとして歯内療法専門医がいます。日本では歯内療法専門医の認知度は低く、顕微鏡普及率も数パーセント。開業当時は歯科医師からも『歯内療法専門医って何?』と聞かれたほどでした。
歯内療法では、手術用実体顕微鏡を使って根管の奥まで目で見ながら治療します。当院は他の歯科医院から紹介された治療困難な症例を扱いますが、他院では抜歯するしかないと言われたケースでも8割の方の歯を残せています。
しかしながら、歯を残したいと希望する患者さんが増えても、歯内療法専門医が不足しているのが現状です。本学の非常勤講師として年に数回実習のお手伝いをしていますが、専門医養成のための機関や制度も必要ではないかと感じています。歯内療法専門医は難しい症例の治療だけを行います。治療が済めば、患者さんには元の歯科医院に戻ってもらうので、一般歯科と協働することが可能なはずです。そのような連携ができれば患者さんはより高度な治療を受けられます。
〝自分の歯〟を残すことのできる歯内療法の良さが広く認識され、治療の環境が整うこと願っています。
口腔保健衛生学専攻

Think Globally, Act Locally.
世界で活躍できる
歯科衛生士になりませんか?
口腔保健学科
口腔保健衛生学専攻 2012年度卒業
松田 悠平
本学は世界大学ランキングでも常に上位にある、国際的な評価が高い大学として認知されている大学の1つです。
ここ口腔保健学科口腔保健衛生学専攻においても充実したカリキュラムのもと、多様で世界的に著名な教員から充実した講義が受講できる環境が整っています。そのため卒業生の進路も多様であり、歯科衛生士として勤務する他、研究者、企業、行政など多岐にわたるフィールドで活躍しています。その活動の幅も広く、日本ひいては世界で活躍している卒業生が多くいます。これは当専攻の国際的な視野に立ったカリキュラムや取り組みが大きく寄与しているのみならず、基本を大切に地道で確実な能力を付与するための環境があるためだと考えます。まさにThink
globally, Act locallyの精神が根付いているこの口腔保健学科口腔保健衛生学専攻で広く活躍できる歯科衛生士になってみませんか?

歯科衛生士は生涯にわたって
人々の健康に寄与する仕事です
大学院医歯学総合研究科 医歯理工保健学専攻
口腔疾患予防学分野 助教
口腔保健学科
口腔保健衛生学専攻 2007年度卒業
安達 奈穂子
歯科衛生士は、お口の健康を通じて、人が胎内にいるときから生涯にわたって、人々に寄り添い、健康を支援できる存在です。
私は口腔保健衛生学専攻の1期生として学びました。歯科衛生士という仕事の魅力を知り、それを体現したいという思いから、臨床経験を積み、大学院で知見を深め、現在は口腔保健衛生学専攻で教育と研究に携わっています。
本学では、医療系総合大学という強みを生かした医学科・歯学科との連携実習、附属病院のみならず充実した臨地実習、多様なバックグラウンドをもつ講師陣による様々な講義・実習・演習を通じて、他では得られない充実した教育を提供しています。この本学ならではのカリキュラムは、学生の自由なキャリアデザインを促し、卒業生は様々な分野で活躍しています。口腔の健康を通じて社会に貢献する、そのような魅力ある歯科衛生士になってみませんか。

歯科衛生士の活躍を支えてくれる、
充実した教育
口腔保健学科
口腔保健衛生学専攻 2013年度卒業
戸田 花奈子
私は入学後、教育・臨床・研究それぞれの分野で活躍する先生の姿に憧れて大学教員の道を志すようになりました。口腔保健学科卒業後は本学大学院修士課程および博士課程を修了し、現在はむし歯や歯周病の効果的な予防システムに関する研究をしています。 大学では歯学部附属病院で各専門外来での実践的な指導を受け、実際に患者さんと接して処置を行う充実した日々を過ごしました。病院の実習で得た経験のおかげで歯科衛生士免許を取得して、早い段階から患者さんを担当させていただきました。さらに医療系総合大学ならではの実習で印象に残っているのは、医学科と歯学科の連携実習です。他分野の学生と意見交換した経験は、患者さんに対する多角的な視点を持つよう意識するきっかけになりました。本学ならではのカリキュラムは学生の自由なキャリアデザインを促し、卒業生は様々な分野で活躍しています。口腔の健康を支えることで社会に貢献する、未来の歯科衛生士をお待ちしています。

各分野で求められる
歯科衛生士の専門性について学ぶ
口腔保健学科
口腔保健衛生学専攻 2012年度卒業
佐藤 未奈子
私は本学を卒業後、千葉県の歯科医院に勤めており、今年度より本学の非常勤講師としても勤務しております。歯科医院での主な業務内容は、歯周基本治療、診療補助等です。成人の約8割が歯周病に罹患していることをご存知でしょうか。私が勤務する歯科医院は歯周病専門であり、重度歯周炎の方が来院されることが多く、専門的知識が求められます。
本学では、講義や実習を通して様々な分野での歯科衛生士の専門性を学ぶことができます。医歯学融合教育や歯学科との連携教育もカリキュラムに含まれており、知識だけではなく、他職種との関わり方を学べる点は、本学の特徴だと思います。また臨床実習では実際に患者さんを担当することができるため、臨床経験を十分に積むことができます。
超高齢社会が加速する中、歯科衛生士の活躍の場が多様化しそれぞれの分野での専門性が求められています。皆様のご活躍を期待しています。
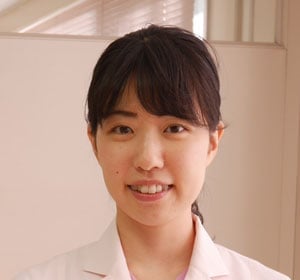
総合病院ならではの口腔ケアを実践
口腔保健学科
口腔保健衛生学専攻 2011年度卒業
木村 文香
現在私は、本学歯学部附属病院口腔ケア外来の歯科衛生士として働いています。外来で患者さんへの口腔衛生指導や専門的なスキルを活用する口腔ケアだけでなく、医学部附属病院に手術のために入院されている患者さんの口腔ケアにも携わっています。口腔ケアの後、患者さんの安心した表情を拝見したり、感謝の言葉をいただいた時には歯科衛生士としてのやりがいを感じ、次への活力となっています。また、医学部への往診に行く中でチーム医療の重要性を痛感したため、今年度より、チーム医療を推進できる指導者を目指すための、「課題解決型高度医療人材養成プログラム」という教育プログラムを履修しています。
口の健康と全身の健康には強いつながりがあることが明らかになってきており、口腔ケアの専門家である歯科衛生士の活躍する場がますます広がっています。本専攻では医療の進歩に伴い変化する社会のニーズに合わせ、授業内容も毎年更新されています。さらに、医・歯学部附属病院との連携によって先端医療を実地に学ぶ体制があるのも、本学の特色の一つであると思います。
今の自分があるのは、学生時代に最先端の知識・技術をご指導してくださった先生方や、ハードスケジュールをこなし、切磋琢磨して成長した仲間のおかげです。本大学での4年間を通して様々なことに挑戦し、歯科衛生士として高い志を持った後輩が増えることを楽しみにしています。
口腔保健工学専攻

現場の歯科技工士を助ける
新製品を開発したい
株式会社トクヤマデンタル
口腔保健学科
口腔保健工学専攻 2018年度卒業
豊田 真奈
口腔保健工学専攻のプログラムで模擬実習を体験し、ものづくりを通じて医療に貢献できる歯科技工士に興味をもちました。幼い頃から手作業で何かを作ることは好きで得意な方でしたので、自分が得意な分野と、多くの人の役に立つ医療が結びつく職業だと感じ、将来の目標として目指すようになりました。
試験片の作り方一つとっても、最初はコツが分からず、苦労することばかりでした。実験には失敗がつきものですが、その都度改善すべき点を見つけ、前向きに取り組んでいます。周囲から学ぶことは多いのですが、歯科技工士資格を持つ私の知識が必要とされるて開発を進めていくことに、仕事の面白みを感じています。
学生時代から、歯科技工士の長時間労働や粉塵などによる健康被害は大きな課題だと感じていました。これまでにない新たな製品を開発することで、歯科技工士の作業の効率化や作業時間の短縮を図り、現場のみなさんの労働環境の改善に繋げたい。そう考えて、この仕事を選びました。歯科医療全体の現状とニーズをしっかり把握し、より便利で使いやすい製品を開発していきたいと考えています。

高い付加価値を身につけ、
多分野で活躍する新たな歯科技工士に
東京科学大学病院
基盤診療部門 歯科技工部 歯科技工士
口腔保健学科
口腔保健工学専攻 2014年度卒業
田村 聡
口腔保健工学専攻では歯科技工の基本的な知識と技術の習得はもちろん、最先端のデジタル機器を使用した実習や海外研修などの幅広いカリキュラムにより、様々な分野で活躍できる人材が育成されています。
4年次の医歯学融合教育では他学科の学生と協力して課題を進めることで、歯科技工士という立場でチーム医療に貢献する方法を学びました。臨床実習では本学大学病院の臨床症例を担当することで、その難しさや緊張感を学び、卒業後の心構えが出来ました。
現在、歯科技工業界は歯科技工士不足や作業のデジタル化など変革の最中にあります。また歯科医療技術の進歩や日本の超高齢化による歯科訪問診療の増加などから歯科技工士へのニーズも変化してきていると感じます。
工学専攻で学ぶ4年間は、新しいニーズに対応する高い付加価値を身につけ、卒業後の様々な選択肢のいずれにおいても自分を助けてくれる素晴らしい経験を得ることができると思います。

矯正器材の商社に就職。
新人社会人として奮闘中
株式会社ロッキーマウンテンモリタ
口腔保健学科
口腔保健工学専攻 2015年度卒業
小野 由貴奈
学生時代に身につけたCAD技術を活かして、現在流行りつつあるマウスピースで矯正できるシステムなどを発展・普及させ、歯科のデジタル化を進めるような仕事がしたいです。また、歯科医師とメーカーとの間に立ち、歯科医療現場で製品を開発・提供していきたいと考えています。
私が入社した会社は取扱製品の約半数が海外メーカーの製品です。海外とのやりとりも多く、英語力も必要とされます。大学3年のときにスウェーデン留学を経験したこともあり、英語力が活かせる職場であることも魅力でした。
現在は、開発・技術サービス課に配属され、新商品開発や技術的なサポート業務を担当しています。過半数が歯科技工士資格を持つ部署で、本学出身の先輩から助けられることも多いです。はじめのうちは社会人としてのマナーも分からず、戸惑ってばかりでした。これまで固定電話を使った経験がほとんどなかったので、電話応対や言葉使いから勉強しました。今は自分の仕事を覚えることに必死で、3000種類もの製品が掲載されている自社カタログを見ながら商品の勉強をする日々です。
大学時代の学び、先輩からご指導いただいたことを活かし、歯科医療現場の発展に貢献していきたいです。
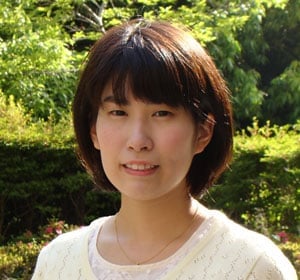
歯科医療技術者として
質の高い医療を提供するために
昭和大学歯科病院歯科技工室
口腔保健学科
口腔保健工学専攻 2014年度卒業
八巻 知里
工学専攻では、さまざまな分野で活躍できる人材を育成するため、歯科技工の専門知識や技術のほか、コミュニケーション能力や国際感覚を養うことにも重点が置かれています。2年全員で参加する海外研修は、先方の学生との交流を楽しみ、英語学習への意欲を高める機会になっています。4年次の医歯学融合教育では他学科学生との意見交換を通して多職種間の相互理解を深め、医療における自分の役割を改めて考えることができ、また臨床実習では患者さんの口腔内補綴装置の製作を通して、技術のみならず歯科医師との意思疎通の重要性を学びました。
私は、現在大学病院の歯科技工室に勤務していますが、医療に携わる全員の連携によって患者さんに満足していただける質の高い歯科医療が提供されること、そして、日々自ら進歩しなければならないということを実感しています。
大学で学んだことを活かし、歯科医療技術者としてこれからますます高みを目指していきたいと考えています。