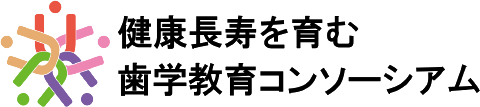講義詳細(シラバス)をダウンロードできます
平成29年度用シラバス
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。
パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
コア科目
|
コース名 |
講義タイトル |
e-lerning |
講義担当教員 |
| 東北大学 |
異分野連携イノベイティブ歯学展開コース |
異分野融合型先端歯学・
歯科医療 | 〇1. 歯学・歯科医療の近年の動向
2. 歯科医療イノベーションに向けての課題
3. 歯学・歯科医学の特徴~異分野融合歯学研究・歯科医療技術開発に向けて~
4. 異分野融合歯学研究・歯科医療技術開発の実例1
5. 異分野融合歯学研究・歯科医療技術開発の実例2
6. 歯学・歯科医療の抱える問題と期待
7. 融合型歯学への転換 口腔とは?歯学とは?
8. 異分野融合歯学の実例 組織としての取り組み
9. 異分野融合歯学の実例 個人としての取り組み |
佐々木啓一,高橋信博 |
| 新潟大学 |
口腔機能管理学コース |
摂食嚥下のメカニズム | 〇 |
井上 誠 |
| 東京医科歯科大学 |
長寿口腔健康科学コース |
長寿を支える硬組織
バイオロジー
|
〇1. 講義の導入。硬組織、骨を構成する細胞の基礎知識
2. 破骨細胞とその関連疾患(大理石骨病、骨粗鬆症、関節リウマチ、歯周病など)。RANKLに関する知識及び癌骨転移との関連。
3. 破骨細胞に関連し、治療薬(ヒト抗ランクル抗体、Bisphosiphonte製剤など)や研究の紹介。
4. 骨芽細胞とその関連疾患。歯の組成。コラーゲンとその関連疾患。骨吸収マーカー、骨形成マーカー。骨細胞の力学的負荷応答。
5. 骨代謝に関するカルシウムの役割、調整機序。
6. 講義フィードバックテスト(解説)
7. 骨格を形成する細胞の発生の基礎的知識
8. 頭蓋縫合早期癒合症、Apert症候群(症候群性頭蓋縫合早期癒合症)
9. 広義のhemifaicial microsomia(第一第二鰓弓症候群、トリーチャーコリンズ症候群) |
中島友紀,井関祥子 |
| 東京歯科大学 |
地域社会に学ぶ新たな歯科医療
プロフェッショナルコース |
テイラード・
コミュニケーション概論 | 〇1.テイラード・コミュニケーション
概論1
2.テイラード・コミュニケーション
概論2
3.テイラード・コミュニケーション
概論3 |
平田創一郎,保坂 誠,佐藤憂子 |
| 日本歯科大学 |
地域連携ケアコース |
地域連携と摂食支援 | 〇1. 地域連携と摂食支援2-1
2. 地域連携と摂食支援2-2
3. 地域連携と摂食支援2-3
4. 地域連携と摂食支援2-4
|
高橋賢晃,菊谷 武 |
各大学の講義内容
東北大学|異分野連携イノベイティブ歯学展開コース
| 4年生 |
授業名 |
e-lerning |
講義担当者予定 |
| 6月7日 |
歯学発の医療機器・技術イノベーション | |
佐々木・鈴木・高田 |
| 6月14日 |
口腔から始まる再生医療 | 〇1.口腔から始まる再生医療 |
福本・江草 |
| 6月28日 |
口腔が支える食と健康 | 〇1.口腔が支える食と健康1
若森 実先生
2.口腔が支える食と健康2
笹野 高嗣先生
3.口腔が支える食と健康3
高橋 信博先生
4.口腔が支える食と健康4
服部 佳功先生
5.口腔が支える食と健康5
西川 正純先生 |
若森・笹野・高橋・服部 |
| 7月5日 |
異業種連携で進化する口腔ケア・リハビリテーション | 〇1.異業種連携で進化する口腔ケア・リハビリテーション1
2.異業種連携で進化する口腔ケア・リハビリテーション2 |
小関・服部 |
| 7月12日 |
社会と医療を繋ぐ歯科情報倫理 | 〇
|
小坂・鈴木 |
| 5年生 |
授業名 |
e-lerning |
講義担当者予定 |
| 10月10日 |
異分野融合型先端歯学・歯科医療 | 〇(コア科目) |
佐々木 |
| 10月17日 |
異分野融合型先端歯学・歯科医療 | 〇(コア科目) |
高橋 |
| 10月24日 |
摂食嚥下のメカニズム① | 〇(コア科目) |
新潟大講師 |
| 10月31日 |
摂食嚥下のメカニズム② | 〇(コア科目) |
新潟大講師 |
| 11月7日 |
地域連携と摂食支援① | 〇(コア科目) |
日歯大講師 |
| 11月14日 |
地域連携と摂食支援② | 〇(コア科目) |
日歯大講師 |
| 11月21日 |
テイラード・コミュニケーション概論① | 〇(コア科目) |
東歯大講師 |
| 11月28日 |
テイラード・コミュニケーション概論② | 〇(コア科目) |
東歯大講師 |
| 12月5日 |
長寿を支える硬組織バイオロジー① | 〇(コア科目) |
東医歯大講師 |
| 12月12日 |
長寿を支える硬組織バイオロジー② | 〇(コア科目) |
東医歯大講師 |
H29年度 受入目標人数:53名 履修者数:50名
新潟大学|口腔機能管理学コース
|
授業名 |
e-lerning |
講義担当者予定 |
| 10月3日 |
ガイダンス、口腔リハビリテーション① | |
前田・井上 |
| 10月10日 |
口腔リハビリテーション② | |
井上 |
| 10月17日 |
口腔機能の変化とその対応① | |
山村 |
| 10月24日 |
地域包括ケアと多職種連携① | |
大内 |
| 10月31日 |
口腔機能の変化とその対応② | |
山村 |
| 11月14日 |
地域包括ケアと多職種連携② | |
大内 |
| 11月21日 |
口腔関連の感染症と多職種連携による管理① | |
寺尾 |
| 11月28日 |
口腔関連の感染症と多職種連携による管理② | |
寺尾 |
| 12月5日 |
成長過程にある口腔機能の発達とその管理① | |
早﨑 |
| 12月12日 |
成長過程にある口腔機能の発達とその管理② | |
早﨑 |
| 1月9日 |
地域連携と摂食支援 | 〇(コア科目) |
日歯大講師 |
| 1月23日 |
テイラード・コミュニケーション概論 | 〇(コア科目) |
東歯大講師 |
| 1月30日 |
長寿を支える硬組織バイオロジー | 〇(コア科目) |
東医歯大講師 |
| 1月下旬 |
摂食嚥下のメカニズム | 〇(コア科目) |
井上 |
| 2月6日 |
異分野融合型先端歯学・歯科医療 | 〇(コア科目) |
東北大講師 |
| 2月13日 |
試験 | |
小野・村上 |
| 2月20日 |
試験(予備) | |
小野・村上 |
H29年度 受入目標人数:45名 履修者数:40名
東京医科歯科大学|長寿口腔健康科学コース
|
授業名 |
e-lerning |
講義担当者予定 |
| 11月24日 |
長寿を支える硬組織バイオロジー | 〇(コア科目) |
中島・井関 |
| 12月1日 |
地域包括ケアシステム論 | 〇1. 超高齢社会を見据えた医療未来予想図(導入、老年学とは。)
2. 超高齢社会を見据えた医療未来予想図(老年学とは。様々な高齢者の紹介。)
3. 超高齢社会を見据えた医療未来予想図( 高齢化について、現状とこれからの社会構造。そこで医療者に求められるものとは。)
4. 超高齢社会を見据えた医療未来予想図(終の住処はどこにある?地域包括ケアシステムの概念図。)
5. みんなで創り上げる「地域包括ケアシステム」(在宅医療の紹介、疾患別自立度低下の経緯、終末期の療養の場所、認知症。)
6. みんなで創り上げる「地域包括ケアシステム」 (地域包括ケア、多職種連携モデル、在宅診療における歯科の役割、在宅診療への教育・研修システム。)
7. より早期からの包括的フレイル予防戦略(健康寿命とは?介護予防の目指すもの。)
8. より早期からの包括的フレイル予防戦略(高齢者の栄養について。)
9. より早期からの包括的フレイル予防戦略(フレイル、サルコペニア、オーラルフレイルとその予防法について。地域包括ケアを通じた高齢社会の創生。) |
東大:飯島 |
| 1月12日 |
異分野融合型先端歯学・歯科医療 | 〇(コア科目) |
東北大講師 |
| 1月26日 |
摂食嚥下のメカニズム | 〇(コア科目) |
新潟大講師 |
| 2月2日 |
在宅における摂食嚥下評価① | 〇1. 導入、摂食嚥下治療の目的とは
2. 症例動画から分かること(口腔領域中心に)
3. 症例動画から分かること(口腔領域以外)
4. 左右の脳血管障害による高次機能障害について
5. 神経両側支配領域、片側支配領域。運動神経の中枢障害、末梢障害
6. 脳幹障害による影響。小脳障害による症状
7. 錐体外路症状について(Parkinson病など)
8. 認知症について。摂食嚥下障害治療の目的(症例動画)
|
戸原 |
| 2月16日 |
在宅における摂食嚥下評価② | 〇(演習形式) |
戸原 |
| 2月23日 |
健康長寿の医療政策学・経済学 | 〇1.導入、日本及び諸外国の高齢化について
2.歯科医療と健康寿命・医療費について、社会保障制度(年金・医療・介護など)の日本の現状
3.国民医療費、歯科医療費の傾向(対GDP、医科医療費、都道府県差)
4.医療保険制度と財源について、目指すは北欧モデル?、国際的に見た我が国
の歯科界の現状、その1まとめ
5.介護保険制度、地域包括ケアシステム
(日本国内における地域差)
6.歯科医師の年収(教育コストとの比較、医科との比較など)・診療報酬について
7.介護報酬について、地域包括ケアの成功の鍵(4都市自治体の活動紹介)。
社会保障制度の再構築へ、その2まとめ
8.歯科医療費について(医療経済効果、混合診療、先進医療、自費診療など)
9.アンケート調査の結果(自費治療/保険治療による違いなど)
10.アンケート調査の結果
(医師及び歯科医師のイメージの違い、医科歯科連携など)、訪問診療について、その3まとめ
|
川渕 |
| 3月2日 |
テイラード・コミュニケーション概論 | 〇(コア科目) |
東歯大講師 |
| 3月9日 |
地域連携と摂食支援 | 〇(コア科目) |
日歯大講師 |
| 3月16日 |
アドバンス病態科学 | 〇(演習形式)
1.イントロダクション
2.資料2導入
3.各班より発表、講師より解説
4.資料3導入
5.各班より発表
6.講師より解説
7.ポストテスト解説 |
大渡 |
H29年度 受入目標人数:53名 履修者数:51名
東京歯科大学|地域社会に学ぶ新たな歯科医療プロフェッショナルコース
|
授業名 |
e-lerning |
講義担当者予定 |
|
口腔機能と生体制御① | |
|
|
内科症候学① | |
|
|
内科症候学②(全3回) | |
|
|
口腔機能と生体制御②(全3回) | |
|
|
臨床社会歯科学(全3回) | |
|
|
歯科患者の全身異常と初期救急対応(全3回) | |
|
|
テイラード・コミュニケーション概論 | 〇(コア科目) |
|
|
テイラード・コミュニケーション概論 | 〇(コア科目) |
|
|
テイラード・コミュニケーション概論 | 〇(コア科目) |
|
|
テイラード・コミュニケーション概論 | 〇(コア科目) |
|
|
実践コミュニケーションと臨床倫理① | |
|
|
実践コミュニケーションと臨床倫理② | |
|
|
長寿を支える硬組織 | 〇(コア科目) |
|
|
摂食嚥下のメカニズム | 〇(コア科目) |
|
|
地域連携と摂食支援 | 〇(コア科目) |
|
|
異分野融合型先端歯学・歯科医療 | 〇(コア科目) |
|
H29年度 受入目標人数:128名 履修者数:134名
日本歯科大学|地域連携ケアコース
|
授業名 |
e-lerning |
講義担当者予定 |
| 8月8日 |
異分野融合型先端歯学・歯科医療 | 〇(コア科目) |
羽村 |
| 8月9日 |
長寿を支える硬組織バイオロジー | 〇(コア科目) |
羽村 |
| 8月17日 |
摂食嚥下のメカニズム | 〇(コア科目) |
羽村 |
| 8月18日 |
テイラード・コミュニケーション概論 | 〇(コア科目) |
羽村 |
| 8月21日 |
多職種共同に必要なコミュニケーション | |
有友 |
| 8月22日 |
摂食機能の発達と障害 | |
町田 |
| 8月23日 |
栄養の評価と指導 | |
須田 |
| 8月24日 |
地域連携と摂食支援① | 〇(コア科目) |
高橋 |
| 8月25日 |
地域連携と摂食支援② | 〇(コア科目) |
菊谷 |
H29年度 受入目標人数:128名 履修者数:138名
「受講生の皆さんへ -キャリアパスにつながる支援-」
健康長寿を育む歯学教育コンソーシアムは健康長寿社会の達成に貢献できる歯科医師の養成を目的としています。本事業の講義を受けて、健康長寿社会の達成に貢献したい!と思った方、ぜひ「お問い合わせ」から連絡をください。どのような研修をするべきか、どのような分野へ進むべきか相談に乗らせていただきます。
講義詳細(シラバス)をダウンロードできます
平成28年度用シラバス
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。
パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
各大学の講義内容
東北大学|異分野連携イノベイティブ歯学展開コース
|
授業名 |
講義担当者予定 |
| 6月1日 |
歯学発の医療機器・技術イノベーション |
|
| 6月8日 |
口腔から始まる再生医療 |
|
| 6月29日 |
口腔が支える食と健康 |
|
| 7月6日 |
異業種連携で進化する
口腔ケア・リハビリテーション |
|
| 7月13日 |
社会と医療を繋ぐ歯科情報倫理 |
|
H28年度 受入目標人数:53名 履修者数:44名
新潟大学|口腔機能管理学コース
|
授業名 |
講義担当者予定 |
| 10月4日 |
ガイダンス、口腔リハビリテーション①
(本学個別科目) |
|
| 10月11日 |
口腔リハビリテーション②
(本学個別科目) |
|
| 10月18日 |
口腔機能の変化とその対応①
(本学個別科目) |
|
| 10月25日 |
地域包括ケアと多職種連携①
(本学個別科目) |
|
| 11月1日 |
口腔機能の変化とその対応②
(本学個別科目) |
|
| 11月8日 |
地域包括ケアと多職種連携②
(本学個別科目) |
|
| 11月15日 |
成長過程にある口腔機能の発達とその管理①
(本学個別科目) |
|
| 11月22日 |
口腔関連の感染症と多職種連携による管理①
(本学個別科目) |
|
| 11月29日 |
口腔関連の感染症と多職種連携による管理②
(本学個別科目) |
|
| 12月6日 |
成長過程にある口腔機能の発達とその管理②
(本学個別科目) |
|
H28年度 受入目標人数:45名 履修者数:43名
東京医科歯科大学|長寿口腔健康科学コース
|
授業名 |
講義担当者予定 |
| 11月25日 |
長寿を支える硬組織バイオロジー(本学コア科目) |
中島 友紀、井関 祥子 |
| 12月2日 |
地域包括ケアシステム論 |
飯島 勝矢
(東京大学高齢社会総合研究機構) |
| 1月6日 |
異分野融合型先端歯学・歯科医療(東北大学コア科目) |
佐々木啓一、高橋信博(東北大学) |
| 1月27日 |
摂食嚥下のメカニズム(新潟大学コア科目) |
井上 誠(新潟大学) |
| 2月3日 |
在宅における摂食嚥下評価 1 |
戸原 玄、中根 綾子、若杉 葉子 |
| 2月10日 |
在宅における摂食嚥下評価 2 |
戸原 玄、中根 綾子、若杉 葉子 |
| 2月24日 |
健康長寿の医療政策学・経済学 |
川渕 孝一 |
| 3月3日 |
テイラード・コミュニケーション概論(東京歯科大学) |
平田 創一郎、保坂 誠、佐藤 憂子(東京歯科大学) |
| 3月10日 |
地域連携と摂食支援(日本歯科大学) |
菊谷 武(日本歯科大学) |
| 3月17日 |
アドバンス病態科学 |
大渡 凡人 |
H28年度 受入目標人数:53名 履修者数:54名
東京歯科大学|地域社会に学ぶ新たな歯科医療プロフェッショナルコース
|
授業名 |
講義担当者予定 |
| 12月12日 |
実践コミュニケーションと臨床倫理① |
|
| 1月13日 |
実践コミュニケーションと臨床倫理② |
|
| 4月11日 |
内科症候学① |
|
| 4月11日 |
口腔機能と生体制御① |
|
| 4月16日 |
内科症候学② |
|
| 4月16日 |
口腔機能と生体制御② |
|
| 4月16日 |
歯科患者の全身異常と初期救急対応 |
|
| 9月26日 |
臨床社会歯科学 |
|
H28年度 受入目標人数:128名 履修者数:145名
日本歯科大学|地域連携ケアコース
|
授業名 |
講義担当者予定 |
| 6月6日 |
多職種共同に必要なコミュニケーション |
|
| 6月13日 |
摂食機能の発達と障害 |
|
| 6月20日 |
栄養の評価と指導 |
|
| 8月29日 |
老年症候群に対する歯科の関わり |
|
H28年度 受入目標人数:128名 履修者数:143名
「受講生の皆さんへ -キャリアパスにつながる支援-」
健康長寿を育む歯学教育コンソーシアムは健康長寿社会の達成に貢献できる歯科医師の養成を目的としています。本事業の講義を受けて、健康長寿社会の達成に貢献したい!と思った方、ぜひ「お問い合わせ」から連絡をください。どのような研修をするべきか、どのような分野へ進むべきか相談に乗らせていただきます。
講義詳細(シラバス)をダウンロードできます
平成26年度用シラバス
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。
パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
各大学の講義内容
東北大学|異分野連携イノベイティブ歯学展開コース
|
講義タイトル |
コア科目 |
講義担当教員 |
| 1月30日 |
異分野融合型先端歯学・歯科医療 |
東北大学 |
|
| 3月20日 |
摂食嚥下のメカニズム |
新潟大学 |
|
| 4月 3日 |
テイラード・コミュニケーション概論 |
東京歯科大学 |
|
| 10日 |
地域連携と摂食支援 |
日本歯科大学 |
|
| 17日 |
長寿を支える硬組織バイオロジー |
東京医科歯科大学 |
|
|
口腔から始まる再生医療 |
|
福本 敏,江草 宏 |
|
歯学発の医療機器・技術イノベーション |
|
鈴木 治,高田雄京,佐々木啓一 |
|
口腔が支える食と健康 |
|
若森 実,笹野高嗣,高橋信博,服部佳功,西川正純 |
|
異業種連携で進化する口腔ケア・リハビリテーション |
|
小関健由,服部佳功 |
|
社会と医療を繋ぐ歯科情報倫理 |
|
小坂 健,鈴木敏彦 |
H26年度 受入目標人数:53名 履修者数:59名
新潟大学|口腔機能管理学コース
|
講義タイトル |
コア科目 |
講義担当教員 |
| 1月13日 |
長寿を支える硬組織バイオロジー |
東京医科歯科大学 |
|
| 27日 |
摂食嚥下のメカニズム |
新潟大学 |
|
| 3月 3日 |
異分野融合型先端歯学・歯科医療 |
東北大学 |
|
| 13日 |
テイラード・コミュニケーション概論 |
東京歯科大学 |
|
| 4月17日 |
地域連携と摂食支援 |
日本歯科大学 |
|
H27年度
実施 |
地域協働と他職種連携 |
|
大内章嗣 |
H27年度
実施 |
口腔環境の変化と対応 |
|
寺尾 豊 |
H27年度
実施 |
発育・加齢と口腔機能 |
|
早﨑治明,井上 誠 |
H27年度
実施 |
口腔機能の変化と対応 |
|
山村健介 |
H26年度 受入目標人数:40名 履修者数:42名
東京医科歯科大学|長寿口腔健康科学コース
|
講義タイトル |
コア科目 |
WebClass |
講義担当教員 |
| 12月12日 |
長寿を支える硬組織バイオロジー |
東京医科歯科大学 |
○ Up!! |
|
| 1月 9日 |
摂食嚥下のメカニズム |
新潟大学 |
○ Up!! |
|
| 16日 |
地域包括ケアシステム論 |
|
○ Up!! |
飯島勝矢 |
| 2月 6日 |
健康長寿の医療政策学・経済学 |
|
|
川渕孝一 |
| 13日 |
在宅における摂食嚥下評価 1 |
|
○ Up!! |
戸原 玄 |
| 20日 |
テイラード・コミュニケーション概論 |
東京歯科大学 |
○ Up!! |
|
| 27日 |
異分野融合型先端歯学・歯科医療 |
東北大学 |
○ Up!! |
|
| 3月 6日 |
在宅における摂食嚥下評価 2 |
|
実習形式 |
戸原 玄,
中根綾子,
若杉葉子 |
| 13日 |
アドバンス病態科学 |
|
実習形式 |
大渡凡人 |
| 20日 |
地域連携と摂食支援担当 |
日本歯科大学 |
|
|
H26年度 受入目標人数:40名 履修者数:55名
※H27.1.23 キックオフシンポジウムが開催されます。
東京歯科大学|地域社会に学ぶ新たな歯科医療プロフェッショナルコース
|
講義タイトル |
コア科目 |
講義担当教員 |
|
実践コミュニケーションと臨床倫理 |
|
|
|
摂食嚥下のメカニズム |
新潟大学 |
|
|
長寿を支える硬組織バイオロジー |
東京医科歯科大学 |
|
|
テイラード・コミュニケーション概論 |
東京歯科大学 |
|
|
臨床社会歯科学 |
|
|
|
内科症候学(生体制御機能) |
|
|
|
異分野融合型先端歯学・歯科医療 |
東北大学 |
|
|
地域連携と摂食支援 |
日本歯科大学 |
|
|
口腔機能と生体制御 |
|
|
|
歯科患者の全身異常と初期救急対応 |
|
|
H26年度 受入目標人数:128名 履修者数:00名
日本歯科大学|地域連携ケアコース
|
講義タイトル |
コア科目 |
講義担当教員 |
| 3月 2日 |
異分野融合型先端歯学・歯科医療 |
東北大学 |
|
| 3日 |
摂食嚥下のメカニズム |
新潟大学 |
|
| 4日 |
テイラード・コミュニケーション概論 |
東京歯科大学 |
|
| 5日 |
多職種協働に必要なコミュニケーション |
|
有友たかね,羽村 章 |
| 6日 |
長寿を支える硬組織バイオロジー |
東京医科歯科大学 |
|
| 9日 |
栄養の評価と指導 |
|
須田牧夫,児玉実穂 |
| 10日 |
摂食機能の発達と障害 |
|
田村文誉,町田麗子 |
| 12日 |
地域連携と摂食支援 |
日本歯科大学 |
|
| 13日 |
老年症候群に対する歯科の関わり |
|
羽村 章,有友たかね |
| 20日 |
地域連携と摂食支援(2) |
日本歯科大学 |
|
H26年度 受入目標人数:128名 履修者数:120名
受講者の声
僕たちはこの講義が始まって、1年目の学生でした。先輩からどんな講義かも聞けず、臨床実習が始まったばかりで色々忙しくて余裕もない時期だったので、ちょっと面倒だなぁと思いながら講義を受けていました。ただ、健康長寿に関する様々な講義、また他大学の特色が現れているコア科目を受講するにつれて、超高齢社会における問題点がよく分かり、この講義の重要性を理解することができました。
講義を終えた今の感想としては、超高齢社会を生きる歯科医師って、大変だなぁということです。通常の歯科治療以上に、高齢者の歯科治療では配慮することが多くあります。全身疾患との関連などはもちろんですが、経済状態や誰がどの程度の介護できるのかなどの社会的要因も治療計画には大きく影響します。また、摂食嚥下リハビリテーションなどと言った、大学病院に来院できる患者さんだけでは学ぶことができない領域の知識も必要であり、、、まだまだこれから勉強が必要であることを強く感じています。
僕はこれから1年間、研修医として過ごします。高齢者の包括的な歯科治療をすぐに完璧に行うことは難しいと思いますが、超高齢社会の歯科医師の一人であることを意識して、1つ1つ学んでいきたいと思います。
(東京医科歯科大学 櫻井祐弥)